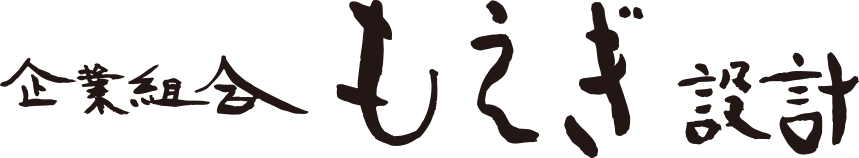清原 2023.06.10
Blogキッチンシンク位置 すまいの細部を考察する Vol.29
キッチン革命というドラマ見ましたか?二週連続の特別ドラマで、一話目は医療の視点から料理をレシピ化する人の話で、二話目が戦後の公営住宅建設にあたりプレス式ステンレス流し台を導入した設計者の話です。

流し台が中央にあって、コンロのスペースは下がっていない部分に置くといった感じです。
4畳半のダイニングキッチンにどうコンパクトにキッチンを組み込むか研究を重ねるのですが、そのレイアウトに注目です。順番が、「冷蔵庫→平場→流し→コンロ」という配置なのです。その当時もそれは画期的な配置として紹介されます。その開発の前は、「冷蔵庫→流し→作業場→コンロ」という現在のよく見るレイアウトと同じなのですが。公営住宅開発時にこれが入れ替わります。その使い方がはっきりと写しだされていなかったのですが、どうも流し台にまな板をかけて使っていたように思われます。切ったものを鍋に入れる、鍋から流しに流すという作業が動かずにできることを目指したようですが、現在に受け継がれていないですね。現在の使い方イメージでは真ん中の作業場(平場)に食材を並べてまな板を置き、切ったものをざるに受け、といったイメージだと思われます。実際どうですか?

コンロの部分は下げられていますが、シンクが中央にあるのです。
そう思いながら自分の家の台所作業を想像すると、流し台とコンロの間でやる作業は材料を切る、ということに特化してもいいような気もします。でもいきなり流しでは困ります。30㎝でも平場が欲しい。まな板は流しに1/3程度はみ出していますが、切ったものを鍋やフライパンに入れる前に、ザルやボウルに分け入れておく物たちもあります。(ほとんどはまな板から直接ですが)そのあとにフライパンから大皿に盛りつけるスペースは欲しいです。そのスペースはどこだ?理想的には配膳台が欲しい。これが流しとコンロの間の平場に混在するのがダメなのかもしれませんね。アイランド配膳台がいい。でも公営住宅ではこれが食卓に直接配膳するということなのでしょう。なるほどコンパクトだ。これなら4畳半ダイニングキッチンは成立するかもしれません。ヨーロッパの素敵なキッチンはほとんどがダイニングキッチンです。そこには戻れませんが、可能性はあるように思います。下の写真も狭いとはいえキッチン部分とテーブル部分は離れています。細長6帖くらいかな。

キッチンを通り抜けた先にダイニングスペースがあるのでしょうか。