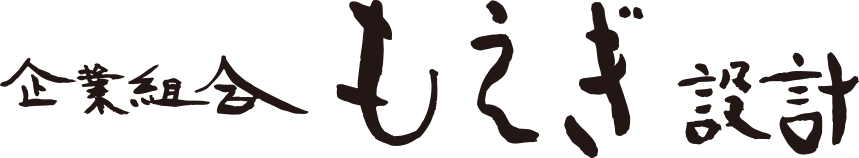山田 2023.01.22
Blog「ウッドデッキ 製作 前編」私のすまいづくりvol.32
<ウッドデッキ製作 前編>
板塀が完成したので、次はウッドデッキに取り掛かります。一応1月中にウッドデッキとアプローチ横の落下防止柵を作る予定です。少し遅れ気味ではありますが。
ネット上でウッドデッキを検索すると様々な作り方が出てきますが、我が家の場合はできるだけ単純で簡単な構造にしています。束を立てて大引を600mmピッチで乗せて、30mm厚のデッキ材を張っていくというだけです。
工程は以下の通りです。
1.材料を塗装し乾燥 2.束石の位置を決める 3.束石を並べる 4.束を建てる 5.大引を並べる 6.デッキ材を貼る
まずは束石の位置を決めていくのですが、地面は砂利が敷かれた状態なので、水平垂直などを出すのがかなり大変です。よく現場でデッキの下は土間コンを打たせて欲しいと大工さんから言われることがあります。雑草が生えにくいのに加え、墨出しや高さの設定など作業が断然楽になるというのを今回実感しました。我が家の場合は今更コンクリートを打つわけにもいかないので、砂利をどかしながら地道に束石を設置していきます。特に難しいのが束石を横にまっすぐに並べるのと、直角に縦に並べる作業です。板塀の際にも使ったレーザー墨出し器を使ったり、水糸を張ったりしながら位置を決めていくわけですが、作業性が悪くなるため水糸を全ての列に張るわけにもいかず、結局大体この辺かなという感じになってしまいます。

デッキ材と大引を塗装し乾燥中。スペースの問題で全ての材料を一気に塗装できないのが辛いところ。

初めはこんな状態。水糸を張って束石の位置を決めていきます。
束石の位置がおおよそ決まれば、次は地面を少し掘り、砕石を入れて転圧し、束石を置き、水平を出します。束石の天端の高さは今回は特に気にしていません。束の高さを調整してデッキの高さを合わせるため。束石が全て据え付けられたら、周りにモルタルを入れて固めます。本当は束石の下にモルタルを敷いてから束石を設置し、水平を微調整しながら固めてやるといいようですが、かなりのモルタルの量が必要となりそうなので割愛しました。周りに入れるだけでも結構なモルタルの量が必要になり、だいぶケチって入れています。

束石が概ね設置し終わった様子。中腰で同じ作業の繰り返しが30箇所。忍耐力が必要です。

モルタル を束石の周りに敷き込みます。手前の束石は羽子板付束石コンクリートと呼ばれる既製品ですが、何故だか真ん中に穴が開いているため、埋めないと雨水が溜まるそうです。
さて、次は束を立てていきます。見た目と作業性を考え、外側は木製束で中は鋼製束としています。鋼製束は支柱部分を回転すると高さを調整できるため、後々微調整が簡単にできるメリットがあります。ただ、鋼製束だけでは結構揺れるため、外壁側の列の何本かは木製束にしていて、デッキ下で木製束同士を板で繋いで剛性を持たせます。根がらみと呼ばれるもので、現在の住宅では使われませんが、京町家など基礎がなく束立ち柱の建物では昔から使われていた技術です。実際に板を張ってみると本当に揺れがなくなったので、そんなことが体感できるのもDIYの楽しさの一つです。

ホームセンターで購入できる鋼製束。サイズも5サイズくらいは店頭に置いてありました。
木製束はレーザー墨出し器を使い、束石ごとに必要な高さを計り、その高さに合わせて大引と同じ90角の桧材を切っていきます。最初は押し切りノコと呼ばれる工具で切ろうと思っていたのですが、材料が大きすぎて入りません。丸のこで切るしかないようです。その場合1回では切れなくて表と裏に分けて切る必要があります。同じ位置で切れるように線をひいてはみますが、中々同じ位置で切るのは難しく、1mm内外の段差ができてしまい、束を立ててみると結構ガタつきます。しょうがないので大きくガタつくところには1mmのゴムシートを張ってガタつきを軽減させてみました。どこでつまづくのかは実際に作ってみないと分からないので、色々いい経験になっています。慣れた大工さんはきっと段差なく切断できるのでしょう、羨ましいです。
木製束を切り終わる工程までで丸4日かかりました。今年の仕事始めは間に有給を取り、10日からだったためだいぶ助かっています。この先は週末しか作業ができないためペースが一気に落ちてしまいます。実際に作ってみると中々予定通りには進んでいきません。 >後編に続く

丸のこで束を切断しているところ。丸のこの扱いは苦手です。

切断した木製束をそれぞれの束石に並べていきます。高さが数ミリしか違わない束もあるため、ちゃんと束石と束に記号を書き込んでやらないと、後々混ざった際に混乱してしまいます。
*当記事の記載内容について妥当性・正確性・最新性を保証するものではありません。当記事の利用により生じたいかなる損害やトラブルに対しても、一切責任を負いません。ご利用の際は、利用者ご自身の責任において行ってください。